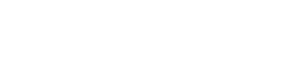米穀周年供給・需要拡大支援事業費補助金(全国)
概要
主食用米の長期計画的な販売や販路拡大等に取組む米穀集荷業者等に補助金を交付!
概要: 産地の自主的な取組により需要に応じた生産・販売が行われる環境を整備するため、主食用米を長期計画的に販売する取組、輸出向け・業務用向け等への販売促進等の取組又は非主食用への販売の取組を行うために必要な経費を補助します。

支援内容
対象費用: 周年供給・需要拡大支援に要する経費,物流効率化実証支援に要する経費,新たな商品開発等の取組に要する経費
助成率: 2分の1以内(事業区分により異なる)
詳細
■事業内容
本事業は、次に掲げる内容により構成するものとする。
1.周年供給・需要拡大支援
産地の自主的な取組により需要に応じた生産・販売が行われる環境を整備するため、主食用米を長期計画的に販売する取組、輸出向け・業務用向け等の販売促進等の取組又は非主食用への販売の取組を行うために必要な経費について、事業実施主体に補助する事業。
2.玄米の推奨規格フレコンを活用した物流効率化実証支援
米の流通合理化を進めるため、玄米の推奨規格フレコンを活用した輸送モデルの実証を行うために必要な経費について、事業実施主体に補助する事業。
3.業務用米、新市場開拓用米等の安定取引拡大支援
業務用米、新市場開拓用米等に関し、産地・生産者と中食・外食事業者、輸出事業者等それぞれのニーズを踏まえた安定的な取引を継続かつ拡大させていくことを目的とした商談会等の開催等の取組、米を利用した新たな商品開発等の取組に対する補助等又は新市場開拓用米の販売拡大の取組を行うために必要な経費について、事業実施主体に補助する事業。
■応募の要件
事業実施主体の公募に応募できる者は、需要に応じた生産・販売を行うために、次に掲げる条件全てを満たす積立てを行っている集荷業者・団体又は事業実施年度中に積立てを開始した集荷業者・団体であって、事業実施年度の前年産又は前々年産の出荷数量が200トン以上の者とします。
(1)生産者等の負担による積立てであること。
(2)積立ての方法、用途、資金管理のルールが明確になっていること。
(3)上記事業内容に掲げるいずれの取組項目にも適切に活用可能であること。
(4)毎年度一定の積立てが維持されていること。
■補助対象経費・補助率
1.周年供給・需要拡大支援
(1) 周年安定供給のための長期計画的な販売の取組に要する経費
補助率:定額(農産局長が別に定める額とする)
(2) 輸出向けの販売促進等の取組に要する経費
補助率:2分の1以内
(3) 業務用向け等の販売促進等の取組に要する経費
補助率:2分の1以内
(4) 非主食用への販売の取組に要する経費
補助率:定額(農産局長が別に定める額とする)
2.玄米の推奨規格フレコンを活用した物流効率化実証支援
(1) 玄米の推奨規格フレコンを活用した物流効率化実証支援に要する経費
補助率:定額(農産局長が別に定める額とする)
3.業務用米、新市場開拓用米等の安定取引拡大支援
(1) 業務用米等に係る商談会等の開催の取組みに要する経費
補助率:定額(農産局長が別に定める額とする)
(2) 米を利用した新たな商品開発等の取組に要する経費
補助率:定額(農産局長が別に定める額とする)、2分の1以内
(3) 新市場開拓用米の販売拡大の取組に要する経費
補助率:定額(農産局長が別に定める額とする)、2分の1以内
■補助金額
補助金の総額は16億5300万円であり、この範囲で事業実施に必要となる経費を助成します。
■補助事業の実施期間
令和4年度の交付決定の日から令和5年3月31日までとします。
■応募方法等
1. 応募書類等の作成及び提出
本事業への応募は、以下の(1)の電子申請を原則としますが、当該電子申請IDを今後取得予定の者及び取得申込手続き中の者又は電子計算機、インターネットその他の電子申請を行う環境が整備されていないため当該申請システムを利用できない者並びに応募申請者側の電子計算機の障害及び通信回線の障害又は停電により応募書類が提出できないおそれがある者については、(2)のその他の申請による応募を受け付けます。
(1) 電子申請
以下のURLから農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(以下「システム」という)により応募してください。
https://e.maff.go.jp
※ Windows 10、11 以外はサポート対象外です。
※ ブラウザは最新のバージョンをお使いください。
※ Microsoft Internet Explorer(IE)では一部の操作に問題が発生する場合があるため、使用できません。
(2) その他の申請
ア 応募書類
別紙により「米穀周年供給・需要拡大支援事業実施主体応募書」を作成し、提出期間内に提出してください。
イ 提出方法等
関係書類を1つの封筒に入れ、「米穀周年供給・需要拡大事業実施主体応募書在中」と表に朱書きをして提出してください。なお、提出書類は返却しません。
※原則として郵送又は宅配便(バイク便も含む。)とし、やむを得ない場合には、持参も可能としますが、FAX 又は電子メールによる提出は受け付けません。
2.提出先
各都道府県別に定められていますので、本事業のHPにて確認してください。